
WEB招待状を送るときのメッセージ例文とマナーを相手別に解説
WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。
カテゴリから探す

WEB招待状(無料)

招待状

席次表

プロフィールブック

席札

エスコートカード

その他のペーパーアイテム

引き出物カード

ヒキタク(引き出物宅配便)

その他の引き出物

プロフィールムービー

オープニングムービー

その他のムービー

プチギフト

両親プレゼント

ウェルカムボード


























ウェルカムスペース・
演出小物

披露宴・二次会景品

結婚式アルバム

コスメ・美容

ウェディングアクセサリー

ドレス・タキシード

フォトウェディング・前撮り

セルフフォトスタジオ

ブライダル保険

結婚内祝い・お返しギフト

カタログギフト

ソーシャルギフト

結婚式 電報・祝電

報告はがき・年賀状・
喪中はがき
グループサイト
イベント情報

結婚式が決まったら、まずはゲストに招待状を送りましょう!
素敵な招待状が届くと、受け取ったゲストもわくわくしてくれるはずです。
しかし招待状の役割や内容について、きちんと理解できていますか?
結婚式の招待状と呼ばれるものには、いわゆる、出欠席用の本状だけが入っているわけではありません。
返事を送っていただくための返信ハガキや、受付を依頼するための付箋など、複数のものを含んで「招待状」と呼ばれています。
ここでは、結婚式の招待状に何を同封するのかを紹介します。
結婚式の招待状には、結婚式の本状以外にもゲスト全員に向けて招待状に同封するものと、一部のゲストだけに向けて招待状に同封するものがあります。
結婚式に招待しているゲスト全員に向けて同封する内容は、本状、返信ハガキ、結婚式場までのマップです。
そして結婚式に招待している一部のゲストにだけ同封する内容は付箋です。
こちらではそれぞれにどんな役割があり、どんなことに注意して結婚式の招待状に同封すればいいのかをご紹介します。
結婚式に招待しているゲスト全員に必須で送らなければいけない内容は、招待状の本状と返信ハガキです。 さらに結婚式場への地図や結婚式場の最寄り駅などについても同封しておくと親切です。
招待状の本状には結婚式についてのお知らせ、挨拶の役割があります。
本状は基本的な構成やマナーが決まっており、作成前に内容を理解する必要があります。
必要事項:披露宴開催の挨拶、開催日時、場所
主催者の名前(新郎新婦なのか?両家両親なのか?)
出欠の返信ハガキの返信期限
結婚式のようにフォーマルな式の招待状は、より丁寧な言葉を使用しなければなりません。
招待状の本状に書く頭語・結語は、「謹啓・謹白」がもっとも適切です。
文字の通り「謹んで申し上げます。」という意味があり、ゲストへの心遣いが感じられます。
さらに本状には「時候の挨拶」を書くのがマナーです。
受け取る相手に四季を感じてもらう挨拶は日本人特有の礼儀です。
ゲストが招待状を受け取る季節を考えて適切な言葉を選びましょう。
句読点は結婚式に不適切な「切る」という言葉を連想するので、本状では使いません。
句読点の代わりに空白で文章を繋ぎます。
また、縁起の悪い「忌み言葉」や「重ね言葉」も使わないよう気を付けましょう。
本状は主催者が新郎新婦か両家両親かで文章の内容が変わります。
両親に援助してもらう場合や両家の親族が多く出席する場合は、両家両親が主催者となります。
本状作成前に両方の文章を理解しておきましょう。
返信期限は返信ハガキではなく、本状のほうに書かれています。
本状は基本的な構成を守れば少しアレンジしても大丈夫です。
結婚式のイメージに合わせた素敵な文章を考えてみましょう。
返信ハガキはゲストに出欠や住所を書いてもらい、返信してもらうハガキです。
各ゲストの個人情報を確認できる、大切な役割があります。
返信ハガキはゲストに出席か欠席、どちらかに丸を付けてもらいます。
氏名、住所、以外に食事のアレルギーについて尋ねる項目があれば、より親切で好印象となります。
返信ハガキは、ゲストに自由なメッセージを書いてもらうスペースを作り、同時に食事のアレルギーについても書いてもらうようにしましょう。
氏名欄は、名前に対して敬意を意味する、「ご芳名」の表記が一般的です。
返信ハガキは縦書き、横書き、どちらでも大丈夫です。
書体やカラーなど、結婚式のイメージに合わせた、個性溢れる招待状を作成しましょう。
招待状に会場までの地図が同封されているとゲストに喜ばれます。
ホテル・専門式場にはすでに印刷された会場案内図が用意されていることが多いので、必要枚数をもらうことが出来ます。
印刷された案内図がなければ自分たちで用意しましょう。
自分たちで案内図を作成する際、会場のホームページ上にある地図を使用したりQRコードを作ったりと方法は様々です。
QRコードを作る場合は、招待状の本状にある住所の横に直接貼り付けることが出来て余分な付箋を節約できるのでおすすめです。
しかし、同封する案内図の作成には注意点があります。
事前にゲストが公共交通機関を使うか自家用車を使うか確認が必要です。
電車なら最寄りの駅名を細かく明記、車なら駐車場の有無を明記、などそれぞれに配慮した案内図になるよう工夫しましょう。
また、年配のゲストが多い場合にQRコードは少し配慮に欠けるかもしれません。
結婚式参列ゲストの内容を把握し、それぞれに合った招待状を準備しましょう。
招待状に同封されていると喜ばれるのは、食物アレルギーの有無を確認できる付箋です。
せっかくの披露宴はゲスト全員に楽しく食事してもらいたいものです。
招待状にアレルギーの有無を確認できる付箋が入っているだけで、安心してくれるゲストもいるはずです。
少しの心遣いで素敵な結婚式を演出できます。
また、式場によっては送迎バスを準備できる場合があります。
事前に式場に確認し、送迎バス有無の付箋を作成しましょう。
同封する際、出発時間や乗り場の明記を忘れないよう注意が必要です。
招待状に同封することでゲストも安心して結婚式に参加してくれます。
こちらでは、結婚式に招待するゲストの中で、一部の人の招待状にだけ同封するものを紹介します。
付箋は挙式への参列・受付・祝辞・余興など、披露宴への参加以外のお願いがある場合、そのゲストのみに同封します。
マナーとしては、招待状を送る前に直接ゲストにお願いしておき招待状に付箋を同封することで、正式なお願いをしたということになります。
招待状を送る前にお願いをせず、急に招待状でお願いしてしまうとゲストが困惑してしまいます。
招待状を送る前に必ず直接お願いをして、了承を得た上で招待状に付箋を同封するようにしましょう。
本状と同じく、付箋にも句読点や「忌み言葉」「重ね言葉」は使えません。
また、同じゲストに結婚式の受付や余興など、複数の題目をお願いする場合もあります。
そういった場合は招待状に同封する付箋も複数になってしまいますので、バラバラになってしまわないようクリップや紐などを使って1つにまとめてから招待状に同封しましょう。
付箋に使う紙はあまりに小さすぎるとゲストが見逃してしまう可能性もあるため、ある程度見やすい大きさにしておくと安心です。
挙式の参列や受付の付箋には、必ず時間を指定して明記しましょう。
受付のお役目があるゲストで挙式の参列もお願いしている場合は、それぞれの時間を明確にして付箋に明記する必要があります。
お役目をお願いしている以上、それぞれの時間管理も自分たちでしっかり行いましょう。
祝辞や余興の付箋は、時間の指定がないのでお願いの文章のみとなります。
このようにゲストによって同封する付箋の内容が違うので、作成時に間違えたものを同封しないよう気を付けましょう。
挙式や披露宴の開催時刻が早かったり、ゲストの家から結婚式場までが遠かったりすると、ゲストがヘアセットや着付けに困ってしまうことがあります。
特に早朝だと、美容院も開いていません。
そういったときのために、結婚式場やホテルで着付けやヘアセットが可能なのであれば、事前にゲストに必要かどうかを確認しておき、予約しておくことができます。
もし着付けやヘアセットを結婚式場でしたいというゲストがいれば、予約時間や場所を記載した案内も一緒に招待状に同封しておきましょう。
2次会の開催・参加が決まっている場合、2次会開催の付箋を招待状に同封するのもよいでしょう。
時間や場所が決まっているなら、内容を明記して招待状に同封することで手間も省けます。
こちらも事前に参加の有無を確認しておきましょう。
また、一部のゲストのみ送迎バスを利用することが分かっている場合は、そのゲストのみ送迎バス案内の付箋を同封しましょう。
もちろん、出発時間や乗り場の明記を忘れずに行いましょう。
こちらでは結婚式の招待状を郵送する前に、気を付けておきたいポイントをご紹介します。
結婚式の招待状に同封するものは、招待状を入れるための封筒に記載した宛名も含めて、プランナーさんや両親に確認してもらうと安心です。
結婚式に向けての準備は招待状だけではないので、スケジュールがタイトなあまり本人たちは気づかないミスをしてしまう可能性もあります。
特に名前や漢字を間違ってしまうとゲストにも失礼なので、必ず第三者に確認してもらうようにしましょう。
結婚式の招待状に同封する返信ハガキ・封筒には必ず慶事用の切手を使用しましょう。
慶事用切手は種類が豊富で、おめでたい「鶴」や「松竹梅」などの和柄が一般的ですが、最近ではハートやキャラクターシールのデザインも多く、招待状を洋風のイメージにしたいときはこちらを使うのも良いでしょう。
慶事用の切手は郵便局で購入することができます。
また、招待状の内容はゲストによって同封するものが異なるので、それぞれの重さが異なり金額も変わる可能性があります。
招待状の封筒に同封するものをすべて入れた上で重さを量り、その重さに応じた金額の切手を購入してください。
切手の金額が不足していた場合、受け取ったゲストに支払わせてしまう、ということにもなりかねませんので注意しましょう。
不安であれば郵便局の局員さんに量ってもらうと安心です。
結婚式に招くゲストすべての招待状を封筒に入れたら、1つ1つ同封するものに間違いがないかを確認しましょう。
挙式に参列してもらうゲストに付箋が入っていなかったり、スピーチをお願いしていないゲストに付箋が入ってしまったりすると、ゲストに対して失礼になってしまいます。
同封すべきものが同封すべき相手の封筒に入っているか、何度も確認を重ねましょう。
結婚式の招待状は、本状だけで構成されているというイメージを持っている人が多いのではないでしょうか?
でも実は、付箋や返信ハガキなど結婚式の招待状に同封するものはたくさんあります。
さらに結婚式を行う会場や、結婚式の招待状を送る相手によって同封する内容は違ってきます。
だからこそ、ゲストに失礼のないように結婚式の招待状を郵送する前にはプランナーさんや両親などに確認してもらうと安心です。
結婚式は大切なイベントであるからこそ、招待するゲストにも気持ちよく過ごしてもらいましょう。

WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。

「招待状の入れる向き」「手渡しする際のマナー」「招待状やハガキの入れ方」etc…実は知らない?封筒のマナーとは
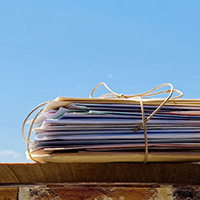
結婚式の招待状に関する疑問と郵送する時に気を付けてほしいことを紹介します

返信ハガキの書き方の注意点をはじめ、よくある質問について解説!

招待状の準備で忘れがちな「付箋」。よく使う付箋の文例や選び方をおさえてしっかり準備しておきましょう

結婚式の招待状を出席で返信したのに欠席しなければならなくなったときのマナー、連絡方法、ご祝儀の有無をまとめて紹介